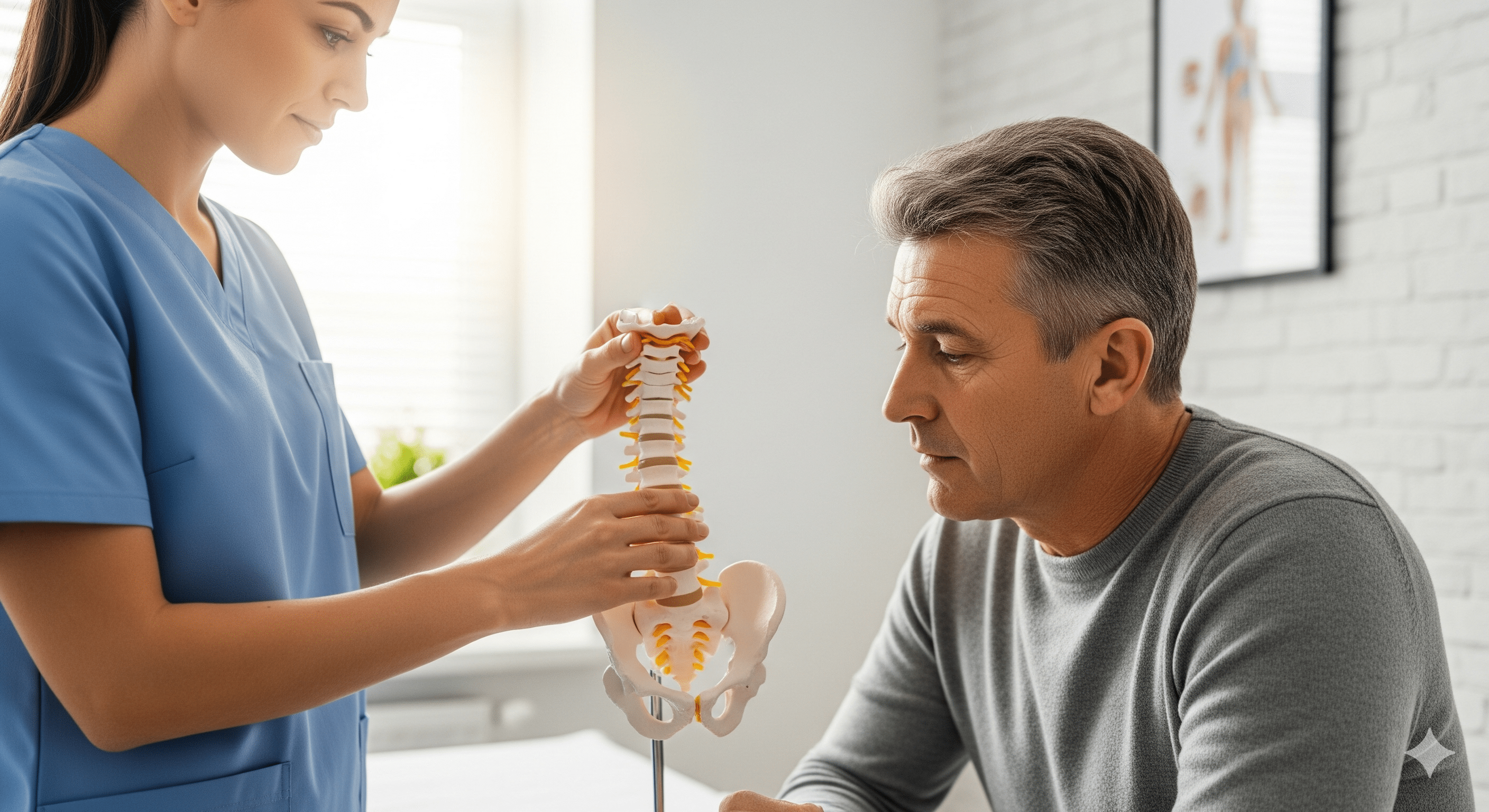その難治性腰痛、なぜ改善しないのか? 日常臨床の“壁”を越えるための新視点
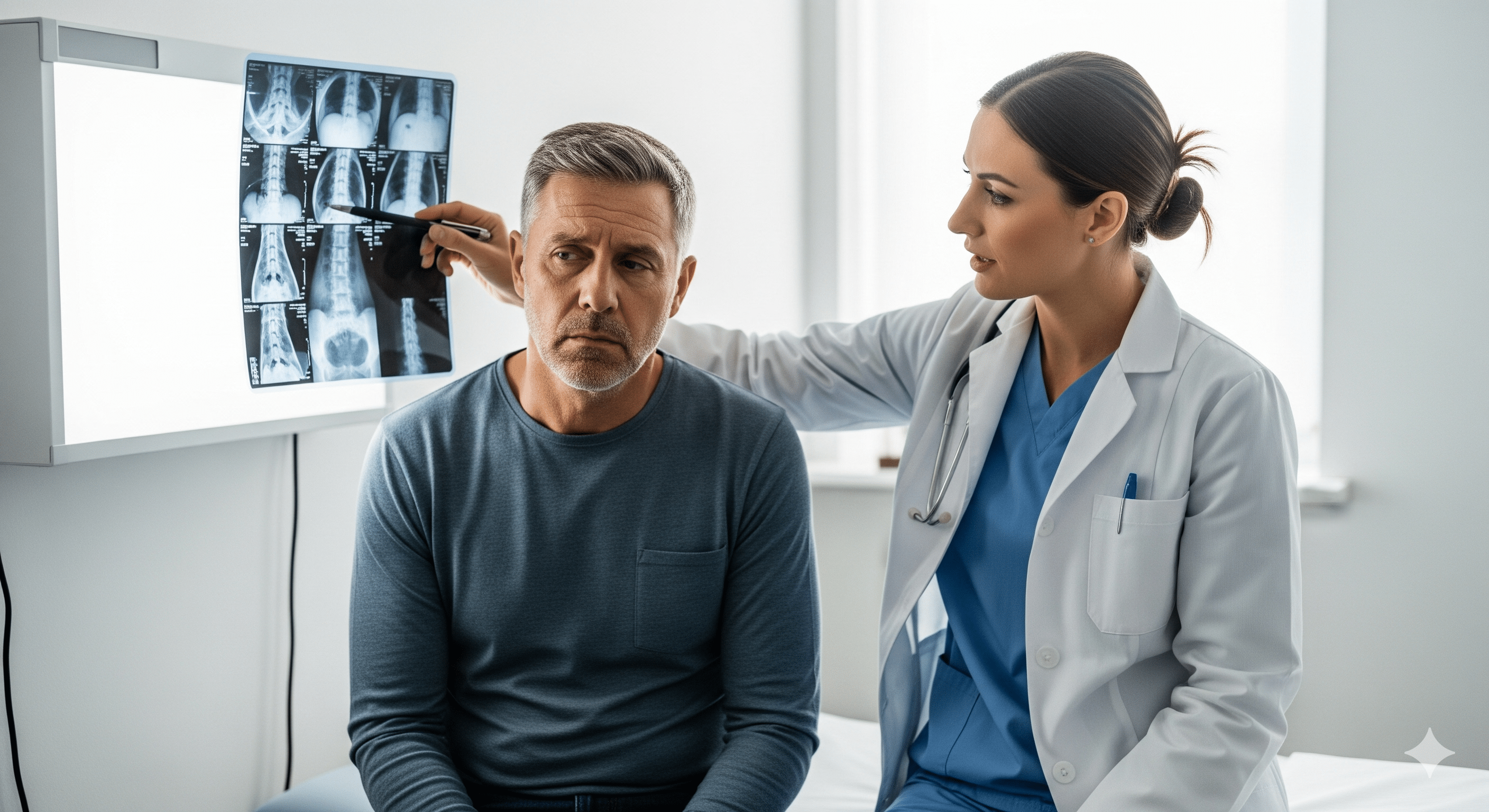
日々の臨床において、標準的なプロトコルに沿って治療を続けているにもかかわらず、思うように症状が改善しない腰痛患者様に苦慮されるケースは少なくないかと存じます。
「これ以上は難しい」「うまく付き合っていくしかない」と説明しつつも、治療家としてのもどかしさを感じておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。今日の治療で改善が見られた患者様が、次に来院されたときには症状が悪化している。その繰り返しに、既存の治療アプローチの限界を感じる瞬間もあるかもしれません。
そうした日常臨床における“壁”を打破する一助となるべく、腰痛治療のパラダイムシフトをこのコラムでは考察してまいります。まず第1回は、我々が拠り所としてきた「腰痛治療の常識」そのものを、改めて注目してみたいと思います。
85%の非特異的腰痛と「画像所見のパラドックス」
ご存知の通り、腰痛はその原因に基づき「特異的腰痛」と「非特異的腰痛」に大別されます。そして、我々が臨床で対峙する腰痛の実に85%が、画像診断では明確な原因を特定できない後者であることは、もはや共通認識です。
さらに、国際腰痛学会のボルボ賞を受賞した著名な研究が示すように、「腰痛のない健常者の76%に椎間板ヘルニアが認められた」という事実は、画像所見と臨床症状が必ずしも一致しないというパラドックスを浮き彫りにします。
この事実は、我々が画像診断に過度に依存することの危うさと、痛みの発生機序をより多角的に捉える必要性を示唆しています。にもかかわらず、臨床現場では長年の慣習から、旧来の保存療法がルーティンとして継続されているケースが見受けられます。
再考すべき腰痛治療のポイント①:安静臥床は機能回復を阻害する
かつて腰痛治療の基本とされた安静臥床。しかし、その有効性については近年、多くのエビデンスによって否定的な見解が示されています。
日本整形外科学会・日本腰痛学会による『腰痛診療ガイドライン2012』が、「ベッド上安静はその効果が低い」と明記していることは先生方もご承知の通りです。過度な安静は、不動による筋力低下、循環不全、さらには心理的な回復阻害因子(黄色信号)を助長しかねません。
むしろ、疼痛を管理しつつ可及的速やかに活動性を維持・向上させることが、機能回復を早め、慢性化を防ぐ鍵である、というのが現代の潮流です。患者指導の場面においても、この転換は極めて重要と言えるでしょう。
再考すべき腰痛治療のポイント②:牽引療法の有効性に対する科学的根拠
理学療法の一つとして広く普及している牽引療法ですが、その有効性についても、ガイドラインは「腰痛患者全般に対し有効である可能性は低い」と断じています。
福島県立医科大学の菊池臣一先生も指摘するように、その効果を支持する質の高いエビデンスは乏しいのが現状です。バイオメカニクスの観点からも、皮膚や表層筋への伸展刺激が、深層の関節や椎間板へ意図した治療的効果をもたらすかは疑問です。
効果に確たる根拠が示されないまま、診療報酬上の都合や慣習によって続けられている側面があるのなら、我々は患者様に最適な医療を提供していると言えるでしょうか。限られたリソースの中で最大限の治療効果を追求するためにも、一度立ち止まってその意義を問い直す必要があるのかもしれません。
今回、我々が日常的に行っている腰痛治療の根底にあるいくつかの「常識」について、最新のエビデンスを基に再検証いたしました。
・画像所見と臨床症状の不一致
・安静臥床の非推奨
・牽引療法の限定的な効果
これらの事実を踏まえると、既存の治療プロトコルだけでは対応しきれない症例が多数存在するのは、ある意味で必然と言えます。
しかし、それは我々の無力を意味するものではありません。むしろ、新たな治療アプローチを模索し、臨床の幅を広げる好機と捉えるべきではないでしょうか。
次回の考察のテーマは、「腰痛の根源的因子としての“重力”」です。
我々が日々、抗いながら活動しているこの物理的ストレスに対し、より直接的にアプローチする視点について掘り下げてまいります。先生方の臨床に、新たな光を当てる一助となれば幸いです。