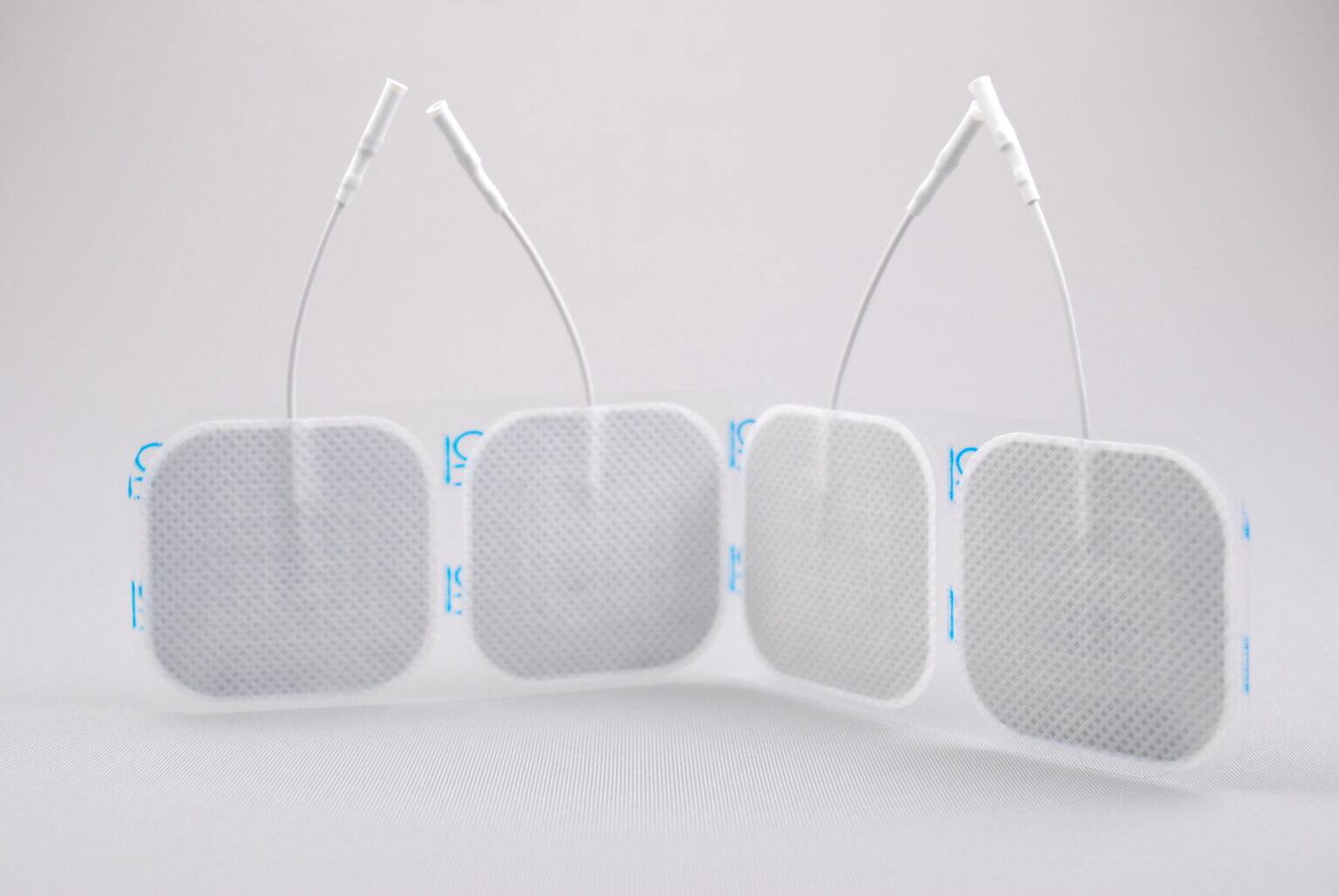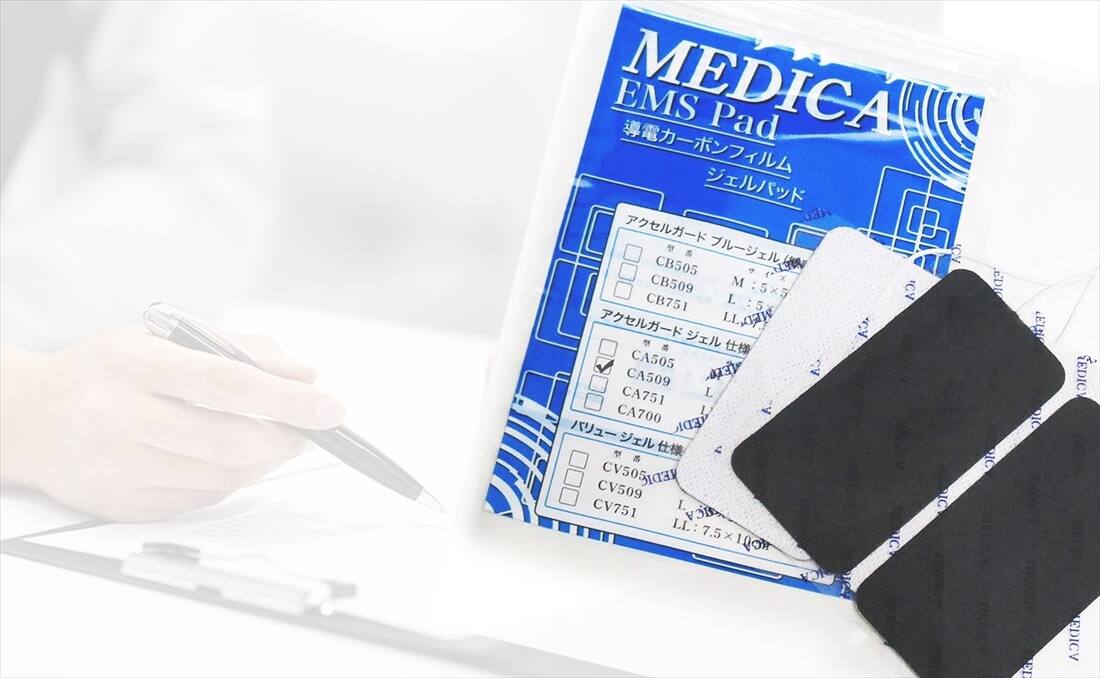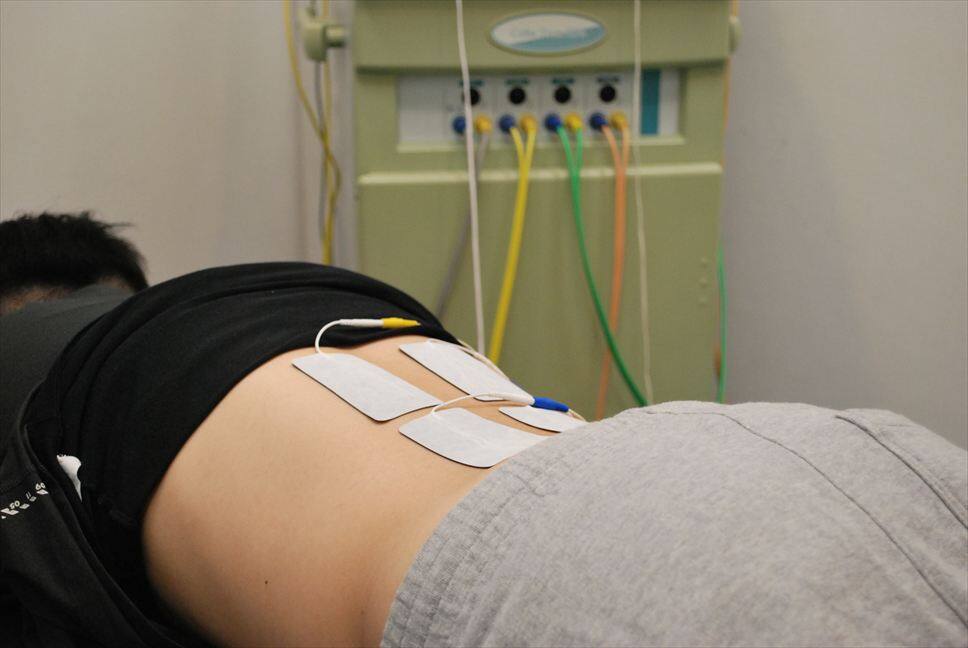EMSとTENSの違い
〜目的に合わせた正しい電気刺激の使い分け〜

医療機関やホームケアの現場では、EMSとTENSという2種類の電気刺激機器がよく登場します。
どちらも皮膚表面から電気刺激を与える点は共通していますが、目的・刺激の仕組み・使用する周波数帯には明確な違いがあります。
EMS(Electrical Muscle Stimulation)
EMSはその名の通り、「筋肉(Muscle)を電気的に刺激して収縮させる」ことを目的としています。
主に運動補助や筋力トレーニング、筋萎縮予防などに用いられます。
刺激は筋肉の運動神経に作用し、自発的な収縮に近い形で筋を動かすのが特徴です。
目的:筋力回復・筋萎縮予防・リハビリ補助
刺激部位:運動神経 → 筋肉
使用例:手術後リハビリ、スポーツトレーニング、体幹強化など
刺激感:やや強め(筋収縮を伴う)
TENS(Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)
TENSは「経皮的電気神経刺激」と呼ばれ、主に疼痛緩和(痛みの軽減)を目的とします。
電気刺激によって痛み信号を脊髄レベルで抑制する「ゲートコントロール理論」に基づいており、
筋肉を動かすのではなく神経の伝達をコントロールすることが主な作用です。
目的:疼痛緩和・血流促進
刺激部位:感覚神経
使用例:腰痛・肩こり・神経痛・関節痛など
刺激感:心地よいピリピリ感(筋収縮は少ない)
併用と選択のポイント
臨床現場では、EMSとTENSを目的に応じて使い分けることが一般的です。
例えば、急性期の痛みにはTENS、回復期にはEMSで筋活動を促進するなど、段階的な活用が効果的です。
また、周波数・パルス幅・出力波形を適切に設定することで、安全かつ効率的な治療が可能になります。
まとめ
EMSは「動かす」ための刺激、TENSは「和らげる」ための刺激。
両者の違いを理解し、症状や目的に応じて正しく選択することが、治療効果の最大化につながります。
メディカの電極パッドは、EMS・TENSのどちらにも対応し、安定した通電と肌へのやさしさを実現しています。